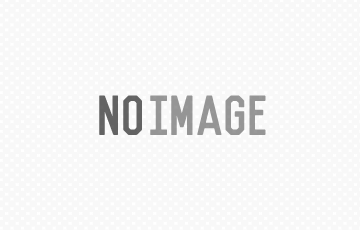年利30%でビットコインが増えるIZAKA-YAの使い方まとめ!好きな分預けて、ほっとくだけ!
ここでは、ビットコインの保有枚数を増やすことができるサービス「IZAKA-YA」について、初心者の方にもわかりやすいよう、具体的かつ詳細に説明します。現在は2025年8月31日時点の最新情報に基づいています。IZAKA-YAは仮想通貨(暗号資産)の世界で注目されているサービスですが、初めての方には馴染みが薄いかもしれません。そこで、基本から丁寧に解説していきます。まず全体像を把握し、次に仕組み、リスク、運営者の実績、さらに税金に関する情報まで深掘りしていきます。
仮想通貨の基本をおさらいすると、ビットコイン(BTC)は世界で最も有名なデジタル通貨で、有限の供給量(最大2,100万枚)と分散型台帳技術(ブロックチェーン)により価値を保っています。保有枚数を増やすということは、単に購入するだけではなく、何らかの方法で自動的に枚数を増やしていくことを意味します。IZAKA-YAはそのためのツールとして機能しますが、投資にはリスクが伴います。まずはサービス概要からご紹介します。
IZAKA-YAのサービス概要
IZAKA-YAは、2024年1月13日にローンチされた暗号資産ウォレットサービスです。主な機能は「レンディング(貸し出し)」と「スワッピング(交換)」で、これらを活用することでユーザーのビットコインや他の仮想通貨を増やしたり、管理したりすることができます。公式サイト(izakaya.tech)によると、IZAKA-YAは「好きな分預けて、ほっとくだけ。最大12%の利率で資産運用」をキャッチコピーとしており、ユーザーは仮想通貨を預けるだけで利息を得られます。
初心者向けに説明すると、ウォレットとは仮想通貨を保管するデジタル上のお財布のようなものです。通常のウォレットはただ保管するだけですが、IZAKA-YAには「運用」機能が付いています。具体的には、ビットコインを預けるとサービス側がそれを貸し出して運用し、ユーザーに利息を支払う仕組みです。これにより、保有枚数が徐々に増えていきます。対応通貨はビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)、USDT(ステーブルコイン)など37種類以上で、2025年時点ではさらに増えて46銘柄に達しています。
このサービスの魅力は、KYC(本人確認)が不要で、メールアドレスだけで登録できる点です。登録は1分以内で完了し、日本語対応のため初心者でも使いやすいUI(ユーザーインターフェース)になっています。Xの公式アカウント(@IZAKAYA_HOROYOI)では、定期的に仮想通貨のニュースやコラムを投稿しており、ユーザー数は1万人を超えています。2025年2月には独自トークン「IZKY」を発行し、エコシステムを拡大。IZKY保有者はスワップ手数料の割引やレンディング利率の優遇を受けられます。
例えば、初心者がIZAKA-YAを使う流れをイメージしてみましょう。まず公式サイトにアクセスし、メールで登録します。次に、国内取引所からビットコインを入金し、レンディングを選択して預け入れます。すると、毎日利息が付与され、保有枚数が自動的に増えていきます。スワッピング機能を使えば、ビットコインを他の通貨に交換して運用することも可能です。これが「保有枚数を増やす」サービスの核心部分です。
2025年8月時点の最新情報として、IZAKA-YAは月間アクティブユーザー数が1万人を超え、キャンペーンで年利20%や30%を提供する期間限定イベントを頻繁に開催しています。Xの投稿では、ビットコイン関連のニュースを共有し、ユーザーとのエンゲージメントを高めています。例えば、2025年8月の投稿では、米国のイーサリアムETFへの資金流入やマイクロストラテジーによるビットコイン購入についてのコラムが公開されました。
ただし、IZAKA-YAはケイマン諸島を拠点とした海外サービスで、日本の金融庁には未登録です。これが後述するリスクにつながります。次は、ビットコインが増える仕組みについて詳しく見ていきましょう。
ビットコインが増える仕組み
IZAKA-YAでビットコインが増える主な仕組みは「レンディング」です。レンディングとは、ユーザーが保有する仮想通貨をサービスに貸し出し、サービス側がそれを必要とする人へ貸して運用し、その利息をユーザーに還元するシステムです。銀行預金と似たイメージですが、IZAKA-YAでは銀行よりもはるかに高い利率が設定されている点が特徴です。
ここでは、具体的な仕組みをステップごとにわかりやすく説明します。
1. 登録と入金
まず、メールアドレスでアカウントを作成し、ウォレットアドレスを取得します。その後、国内の仮想通貨取引所(例:GMOコインなど)からビットコインを入金します。このとき、IZAKA-YAは「トラベルルール(送金時の本人確認ルール)」の制限を受けにくいのが大きな利点です。
2. レンディングの選択
ウォレット画面内にある「レンディング」メニューから、ビットコインを選択します。そして、預け入れる数量と期間を指定します。
期間は短期3日間のキャンペーンから最長365日まで幅広く選択可能です。標準利率は最大12%ですが、キャンペーン時には年利20%〜30%の特別利率が適用されることもあります。
3. ロックアップと運用
ビットコインを預け入れると、一定期間その通貨はロックされ、IZAKA-YA側が運用を行います。運用先は具体的に公開されていませんが、主に借りたいトレーダーや機関投資家に貸し出し、利息を発生させます。
さらに、この利息は毎日自動的に付与され、複利運用(利息に対しても利息がつく仕組み)が可能です。
4. 利息の受け取り
設定した期間が終了すると、元本と利息が返還されます。
例えば、1BTCを年利12%で1年間預けた場合、約0.12BTCが利息として増えます。キャンペーンを活用すればさらに高い利回りを得られるケースもあり、実際には3日間の短期で年利100%(短期高利回り換算)となる例も存在します。
なぜビットコインが増えるのか?
サービス側は、ユーザーから預かったビットコインを高利で貸し出し、その手数料の一部を差し引いてユーザーに還元しています。2025年現在、ビットコインの需要は高く、ETFへの資金流入や企業による大量保有が進んでいるため、貸出利率は比較的安定しています。
実際に、Xの投稿では、こうだい氏というユーザーが「0.75BTCを運用し、利息で0.15BTC増えた」という事例を紹介しています。
スワッピング機能でさらに増やす
IZAKA-YAには「スワッピング機能」もあり、ビットコインをイーサリアム(ETH)など他の通貨に交換し、高利率のレンディングで運用することが可能です。
さらに、手数料は業界最安水準で、独自トークンであるIZKYを使えばスワップ手数料をさらに割引できます。
初心者向けの具体例
例えば、10万円分のビットコイン(約0.01BTC)を年利20%のキャンペーンで3日間預けた場合、数円〜数十円分が増える計算になります。小額からでも試せますが、為替変動(ビットコイン価格の上下)によっては、元本の価値が変わる点に注意が必要です。
このように、IZAKA-YAを使えば「ほったらかし運用」で保有枚数を増やすことが可能ですが、逆に減ってしまうケースもあります。次で詳しく解説します。
逆にビットコインが減ることはないのか?
基本的に、IZAKA-YAのレンディングは元本保証型ではないものの、システム上は利息で増える設計のため、直接的にビットコイン枚数が減ることはありません。預けたビットコインはロックされた状態で運用され、設定した期間終了後には原則として返還されます。
しかし、以下のような間接的なリスクによって、資産価値が実質的に減る可能性があります。
1. 価格変動リスク
ビットコインの市場価格が下がると、枚数自体は増えても資産の日本円換算価値が減少します。
例えば、1BTCを預けて利息で0.01BTC得ても、ビットコインの価格が半分に下がれば、結果的に資産価値は実質的に損失となります。
2. 運用失敗リスク
IZAKA-YAが貸し出したビットコインを、借り手側から回収できないケースが発生すると、元本が減る可能性があります。
ただし、2025年8月現在、IZAKA-YAにおいてそのような報告はありません。
3. 手数料や税金による減少
ビットコインを出金する際の手数料やスワップ時の取引コストによって、最終的な保有枚数がわずかに減ることがあります。
さらに、利息で得たビットコインには税金がかかるため、手取りベースでは減ってしまう可能性もあります(詳細は後述)。
実際のユーザー反応
Xでは、「毎日少しずつ増えているのが嬉しい」というユーザーの声がある一方、価格下落時には「思ったより増えた実感がない」といった不満も見られます。基本的には「減らない設計」ではありますが、相場変動リスクや手数料、税金などを考慮した資産管理が必要です。
短期キャンペーンを活用して複利で運用すると、増加効率が高まりますが、同時にリスク管理も欠かせません。
次は、ハッキングやサービス停止など、より深刻なリスクについて詳しく解説します。
ハッキングやサービス停止のリスクは無いか
IZAKA-YAは便利なサービスですが、リスクがまったくないわけではありません。主なリスクとして、ハッキング、サービス停止、そして日本の金融庁に未登録であることによる規制リスクが挙げられます。
ただし、IZAKA-YAはセキュリティ対策として、Fireblocks社のMPC(マルチパーティ計算)とHSM(ハードウェアセキュリティモジュール)を導入しています。さらに、二要素認証(2FA)や定期監査も実施しており、一定レベルで不正アクセスを防止しています。
とはいえ、絶対的に安全であるとは言い切れません。
ハッキングリスク
-
想定リスク
ハッカーがIZAKA-YAのシステムに侵入し、ユーザー資産を不正に盗む可能性です。過去には、FTX崩壊をはじめとする大手仮想通貨サービスでハッキング被害が多発してきました。 -
IZAKA-YAの対策
Fireblocksは世界で2,000社以上が採用している高い信頼性を持つセキュリティ技術です。秘密鍵を分散管理するため、単一障害点を作らず、一度の攻撃で全資産が盗まれるリスクを最小化しています。2025年8月現在、IZAKA-YAではハッキング被害の報告はありません。 -
発生時の被害想定
仮に発生した場合、最悪のケースではユーザー資産のほぼすべてが失われる可能性があります。例えば、1BTCを預けていた場合、そのまま数百万円の損失になるケースも考えられます。保険制度は現状整備されていないため、資産を取り戻すことは困難です。初心者の方は小額から始め、必ず2FA(二要素認証)を有効化することを強くおすすめします。
X上では「IZAKA-YAのセキュリティレベルは高い」という評価もある一方、「海外サービスなので信用できるのか不安」という声も散見されます。
サービス停止リスク
-
想定リスク
運営会社の経営破綻、規制強化、日本からの利用制限などにより、サービスが突然停止する可能性があります。その場合、ウォレットにアクセスできなくなり、資産を引き出せない状態になる恐れがあります。 -
対策
IZAKA-YAはケイマン諸島に登録されているため、日本国内の金融庁の直接的な監視は受けていません。柔軟な運営は可能ですが、その分、規制面でのリスクは高まります。日本の金融庁が利用停止を勧告した場合、資産が引き出せなくなる可能性も考えられます。 -
被害想定
仮にサービスが突然停止した場合、資産が凍結され、引き出しが数ヶ月できなくなる、もしくは最悪の場合は永久に引き出せない可能性もあります。過去の事例では、Celsius Networkが経営破綻した際、ユーザー資産の総額数百億円が失われたとされています。IZAKA-YAのユーザー数は約1万人なので、総資産規模は数億円程度と推定されますが、被害が発生すれば大きな損失につながります。
その他のリスク
-
規制リスク
日本国内で未登録サービスを利用しているため、金融庁による利用禁止命令が出る可能性があります。また、税務署からの調査や追徴課税につながるケースもあります。 -
運営透明性リスク
運営会社の代表者情報が公開されておらず、ケイマン諸島および香港の法人で運営されているため、透明性が低いです。このため「詐欺サービスなのではないか」という疑念を持つユーザーも一定数います。 -
流動性リスク
レンディングでロック中の資産は、途中で出金できません。急激な価格変動があった場合、想定通りに資産を動かせないリスクがあります。
全体的に、IZAKA-YAはセキュリティ対策を強化していますが、リスクを完全にゼロにすることは不可能です。万が一の事態が発生した場合は、被害額が大きくなる可能性があるため、資産の分散管理が強く推奨されます。
リスクがある場合の想定と被害規模
リスクが現実化した際の被害を、ケースごとに具体的に見ていきましょう。
1. ハッキングが発生した場合
-
発生確率:低い(Fireblocks採用のため)
-
被害想定:発生すれば全ユーザーの資産が失われる可能性あり
-
被害規模:サービス全体で推定数十億円、個人では1BTC(約1,000万円相当)を失う可能性も
2. サービス停止の場合
-
発生原因:経営破綻、規制強化、日本国内での利用制限
-
被害想定:ウォレットにアクセスできず、資産が凍結される
-
具体例:数ヶ月〜数年単位で引き出せない状態が続く可能性あり
-
過去事例:Celsius Networkの破綻時、ユーザーは50%以上の損失を被りました。
3. 規制介入の場合
-
発生原因:日本の金融庁が未登録サービスを禁止
-
被害想定:資産が強制的に没収される可能性は低いものの、出金制限や口座凍結が起きる恐れがあります。
-
間接的な損失:資産が引き出せない間にビットコイン価格が下落し、損失が拡大するリスクがあります。
初心者の方は、こうしたリスクを十分に理解した上で「余裕資金」での利用を検討することが大切です。X上では「IZAKA-YAは安全」という意見もありますが、過去の事例を考えると、資産管理は慎重に行う必要があります。
運営者(運営会社)の実績
IZAKA-YAの運営は Izakaya Limited というケイマン諸島に登録された企業が行っています。さらに、香港に関連法人として Brothers Izakaya International も存在します。ただし、代表者情報が公開されていないため、運営の透明性はやや低いといえます。
運営実績の概要
-
2024年1月:IZAKA-YAを正式にローンチ
-
2024年末:ユーザー数が1万人を突破
-
2025年2月:独自トークン IZKY を発行し、独自エコシステムを拡大
-
提携先:Fireblocks(セキュリティ技術提供)、CryptoPanda(円交換パートナー)
-
情報発信:X公式アカウントで仮想通貨関連のニュースやコラムを定期的に発信
これらの実績により、一定の信頼性は得られている一方、金融業界やWeb3領域での経験値はそれほど多くないと見られています。このため、一部ユーザーからは「長期的な安定性は未知数」「透明性が不足している」といった懸念の声もあります。
2025年8月時点ではサービス自体は安定して稼働しており、大きなトラブルは発生していません。ただし、運営体制や透明性に関する不安を完全に拭い去ることは難しいため、過度な資産集中は避けることが推奨されます。
ビットコインが増えたり減ったりした場合の確定申告
2025年8月31日時点の日本の税制に基づいて、IZAKA-YAでビットコインが増減した場合の確定申告について詳しく解説します。
結論から言うと、IZAKA-YAで得た利益や損失は現時点では「雑所得」として扱われ、総合課税の対象になります。税率は所得に応じて 15%〜55% の範囲で課税されます。
1. ビットコインが増えた場合(利益が出た場合)
IZAKA-YAでレンディングにより得られた利息分は「雑所得」となります。特に、年間で得た雑所得が 20万円を超える場合 は確定申告が必要です。
具体例
-
1年間で利息 0.1BTC を獲得した場合
-
ビットコイン価格が 1BTC=1,000万円 なら、
0.1BTC × 1,000万円 = 100万円の利益 -
この100万円は雑所得として課税対象となり、所得税率が30%なら税額は約30万円です。
2. ビットコインが減った場合(損失が出た場合)
IZAKA-YAでのレンディング中に損失が発生した場合、その損失は「雑所得内」であれば損益通算が可能です。
ただし、株式やFXの損失とは異なり、仮想通貨の損失は他の所得(給与所得や事業所得など)と相殺できません。あくまで同じ雑所得内でのみ通算可能である点に注意が必要です。
3. スワップ機能を使った場合の課税
IZAKA-YAのスワッピング機能を使ってビットコインをイーサリアム(ETH)やUSDTに交換した場合、その時点で利益が確定したとみなされ、課税対象となります。
例
-
1BTCを500万円で購入
-
ETHに交換した時点で1BTCの市場価格が800万円になっていた場合
-
800万円 – 500万円 = 300万円の利益
この300万円は交換時点で雑所得として課税されます。
4. 最新の税制動向(2025年時点)
2025年現在、政府内で仮想通貨の課税方法について見直し議論が進んでいます。特に、仮想通貨を株式と同様に 申告分離課税(税率20%) に統一する案が検討されていますが、現時点ではまだ施行されていません。
また、株式を通じたビットコイン投資(例:メタプラネット株など)であればNISA口座を利用して非課税投資が可能です。こうした制度を併用すれば、課税負担を減らせるケースもあります。
5. 確定申告の重要ポイント
-
年間の雑所得が 20万円超 なら申告が必要
-
利息・スワップ利益・売却益すべて課税対象
-
損失は雑所得内でのみ通算可能
-
申告漏れの場合は追徴課税や延滞税のリスクあり
特に、IZAKA-YAのような海外サービスを利用する場合、取引履歴が自動で税務署に連携されるわけではないため、ユーザー自身で正確に記録・管理する必要があります。
詳細な税計算例
ビットコイン価格が 1BTC=1,000万円 のケースを想定します。
-
1BTCを預け、利息で 0.05BTC を得た場合
-
0.05BTC × 1,000万円 = 500万円の利益
-
所得税率が30%の場合、税額は150万円 です。
さらに、レンディング中にビットコイン価格が下落して損失が出た場合には、その損失分を雑所得内で相殺することができます。
申告漏れのリスク
仮想通貨取引は税務署も重点的に監視している分野です。申告を忘れると、通常の税額に加えて追徴課税や加算税が課される可能性が高いため、初心者の方は早めに税理士へ相談することをおすすめします。
まとめと注意点
IZAKA-YAは、ビットコインをはじめとした仮想通貨を「ほったらかし運用」で増やすことができる便利なサービスです。特に、レンディング機能を活用することで、仮想通貨を預けるだけで利息が付与されるため、初心者でも比較的手軽に資産を増やす体験ができます。
しかし、この記事で詳しく解説したとおり、リスクがまったくないわけではありません。ビットコインの価格変動リスク、サービス停止やハッキングのリスク、そして税務上の注意点など、押さえておくべきポイントが数多く存在します。
IZAKA-YAを利用する際の重要ポイント
-
小額から始めることを推奨
仮想通貨は値動きが激しく、元本保証もありません。最初は生活に影響しない範囲で小額から始め、サービスの使い勝手を確認しましょう。 -
最新情報を常にチェックすること
キャンペーン内容、対応通貨、利率、規制などは頻繁に変わります。IZAKA-YAの公式サイトや公式Xアカウントで最新情報を定期的に確認することが重要です。 -
リスク管理を徹底すること
-
資産をIZAKA-YAに一点集中させない
-
ハードウェアウォレットなど複数の管理方法を併用する
-
2FA(二要素認証)を必ず有効化する
-
-
税務上の対応を忘れないこと
IZAKA-YAで得た利息やスワップ利益は「雑所得」として課税されます。取引履歴をきちんと記録し、確定申告を適切に行うことが大切です。
初心者へのアドバイス
-
リスクとリターンのバランスを意識する
高利回りキャンペーンは魅力的ですが、同時にリスクも高くなる可能性があります。特に短期の高利率イベントは、元本がロックされる期間が短い分、資産を流動的に動かしやすい一方で、市場変動に対応しにくくなる点に注意してください。 -
情報源は公式と信頼できるコミュニティを活用する
Xや仮想通貨関連フォーラムには、実際にIZAKA-YAを利用しているユーザーの体験談や運用報告が多く投稿されています。これらの情報は非常に参考になりますが、誤情報も多いため、最終的には公式サイトの情報で判断することが安全です。
この記事のまとめ
-
IZAKA-YAはビットコインや仮想通貨の保有枚数を増やせるウォレットサービス
-
レンディング機能で預けた通貨を自動運用し、利息で資産が増える仕組み
-
高利回りキャンペーンを活用すれば効率的に資産を増やすことが可能
-
ただし、価格変動リスク・運営リスク・ハッキングリスクはゼロではない
-
税金や規制の影響も考慮し、取引履歴を正確に管理することが重要
IZAKA-YAは確かに魅力的なサービスですが、「安全に資産を増やす」ためにはリスク管理が欠かせません。投資は自己責任で行う必要があるため、しっかりと情報収集しながら慎重に判断してください。
この記事は、2025年8月31日時点の最新情報に基づいて執筆しました。今後のサービス内容や規制状況によって条件が大きく変わる可能性もありますので、常に最新情報を確認しながら利用することをおすすめします。
もし疑問点があれば、IZAKA-YAの公式サポートやX公式アカウントを活用するとよいでしょう。